 |
●移動平均線 「移動平均線」は、毎日のジグザグした価格変動を滑らかな曲線で表現することによって トレンドの見極めが行いやすいように工夫されたテクニカル指標です。 マーケット価格(終値・高値・安値)の過去何日(週・月)分かの平均値を計算して、グラフにします。 移動平均線は、期間設定の長さにより、短期線、中期線、長期線に分類することができ、それらの期間の違う線の交錯具合による判断も行います。 期間設定を長期にすれば、移動平均線の動きは緩やかになり、長期的なトレンドの確認が出来ますが、反面、価格変化に対する反応が遅いという欠点があります。 移動平均線のメリット 日々の相場の値動きに惑わされずに、トレンドを把握する上で役立つ。 移動平均を見る際に最も重要なことは、まず、その傾きの方向性を見ることです。 傾きが上向きの時は、トレンドが上向きであると判断でき、傾きが下向きの際にはトレンドは下向きと判断できます。また、価格が移動平均より上の時には、市場は強気の状態といえ、市場が弱気になると価格は移動平均より下になります。 |
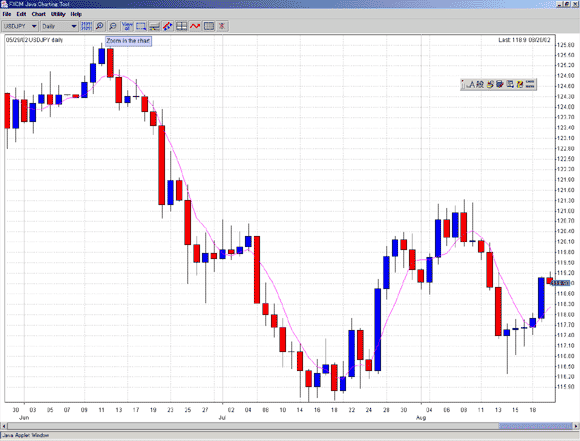 |
| 移動平均線による相場の見方 移動平均線を用いた具体的な判断手法としては、J・E・グランビルによるグランビルの法則が有名です。 これは、値段と移動平均線の関係に注目し、売買ポイントを8つの法則にまとめています。 ★グランビルの法則 <グランビルの法則の図> |
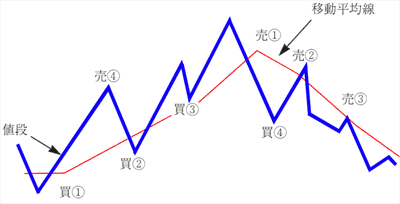 |
| 買いポイント1 移動平均線が下向きから、横ばいもしくは上向きかけている状態で、日足が移動平均線を上抜いたとき 買いポイント2 移動平均線が上昇しているときに、価格が移動平均線を下回った場合 買いポイント3 上昇中の移動平均線に向かって、価格が上方から一旦、下落したものの、移動平均線を割り込まずに、再度上昇に転じたとき 買いポイント4 移動平均線・価格とも下落基調にある中で、価格が移動平均線から大きく乖離して下落した場合。移動平均線から大きくかけ離れて動いた場合には、価格もしくは日数(日柄)のどちらかにより、修正されることが多い。 売りポイント1 移動平均線が長期間、上昇を続けた後、横ばい、もしくは下落し始め、価格が移動平均線を下抜けたとき 売りポイント2 移動平均線が下降中に価格が、移動平均線を上回ったとき 売りポイント3 下降中の移動平均線に向かって価格が下方から上げてきたが、突破できずに再び反落したとき 売りポイント4 移動平均線が上昇中であっても、相場が大きく乖離して高騰したとき |
| ●パラボリック(Parabolic)
パラボリックとは、「放物線状の」という意味を持ちます。 売買ポイントをSAR(ストップ・アンド・リバース)と呼ばれるラインが表す形から名づけられました。 パラボリックはトレンドをとらえ、そのトレンドが反転した場合に、ポジションを途転することを目的としています。 売買ポイントは、チャートの価格線とSARが交差した点です。つまり、上昇しているSARが下降中の価格線と接触した地点が売りポイント、下降しているSARが上昇中の価格線と接触した点が買いポイントになります。 |
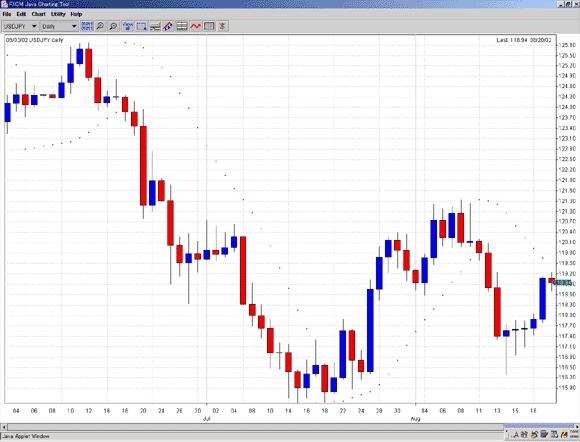 |
| パラボリックは、マーケットが大きく動いているときには、役立ちますが、もちあい状態で値動きが小さいときには、成果が上がりません。 |
| ●ボリンジャーバンド(Bollinger Bands)
ボリンジャーバンドは、価格変動の標準偏差を用いて移動平均線の上下に「バンド」を作り、実際の価格とバンドとの相対的な位置関係から将来の価格の動きを統計的確率論から判断する指標です。 基本的な読み方は「バンド」の上限に接近したが上抜けなかった場合、マーケットは上げ過ぎと判断し「売りサイン」、「バンド」の下限に価格が接近したが下抜けなかった場合、マーケットは下げ過ぎと判断し「買いサイン」とします。 統計学上では、正規分布である場合、平均値±1標準偏差の中に入る確率は約68%、平均値±2標準偏差の中に入る確率は約95%、平均値3標準偏差の中に入る確率は約99%です。 このため、大きくバンドから乖離した動きをする可能性は、低い確率となり、上限もしくは下限に達した価格は、反転する可能性が高いといえます |
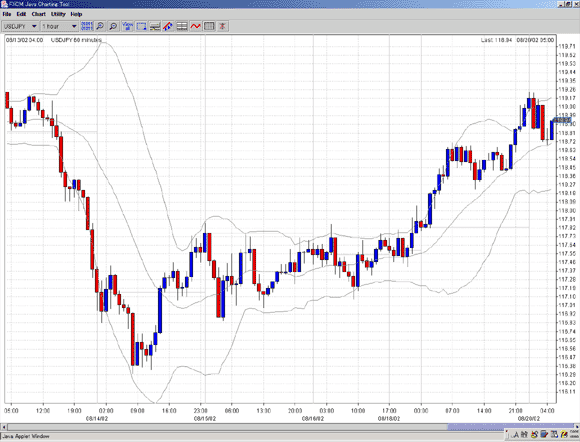 |
| ボリンジャーバンドは、ボラティリティー(変動率)が増加すると、バンドの幅が広がり、ボラティリティーが減少すると幅が狭まります。狭いボリンジャーバンドは動きの少ない平板なマーケットを表しています。 通常、価格の動きはボリンジャーバンドの範囲で収まりますが、非常に狭いボリンジャーバンドにおいて、バンドを突き破る勢いで上昇する場合には、大きなトレンド変化を示す場合が多く注意が必要です。 |
|
|
| - Home
-
|
| Copyright (c) 2002-2004 http://88888.ne.jp xu@88888.ne.jp ALL RIGHTS RESERVED |